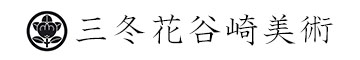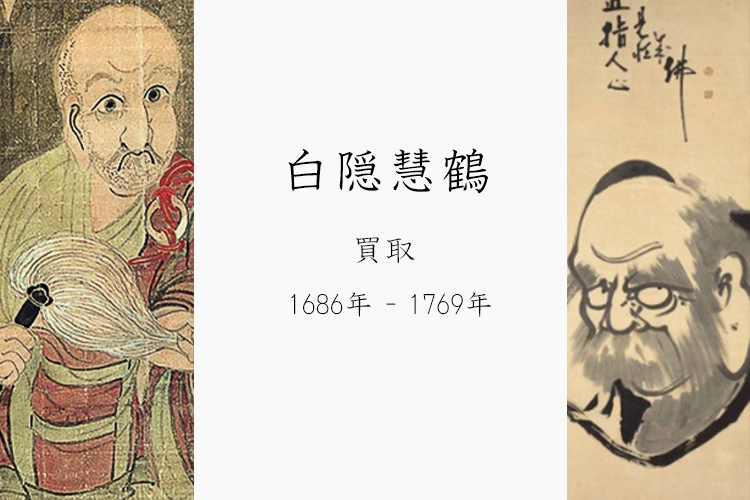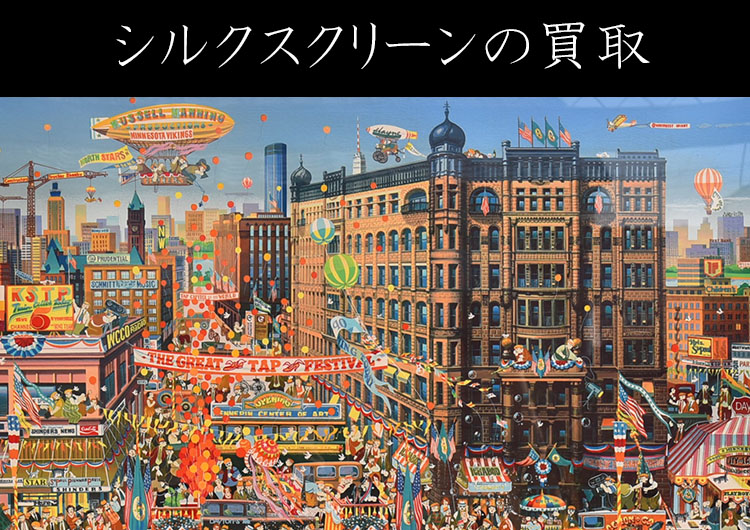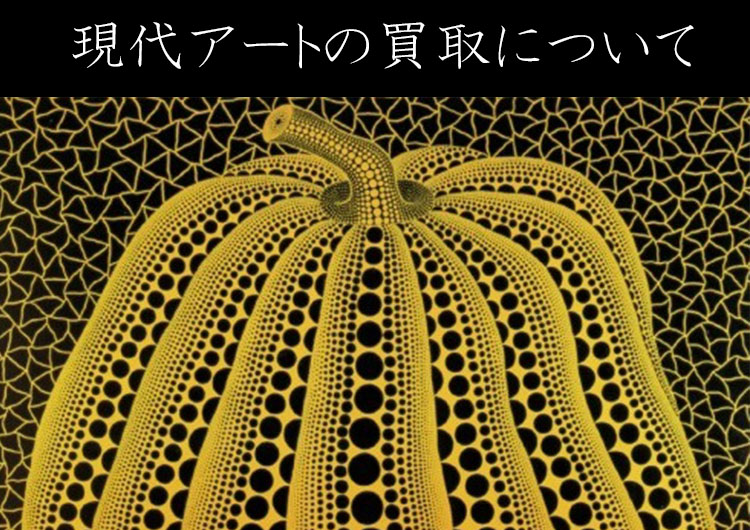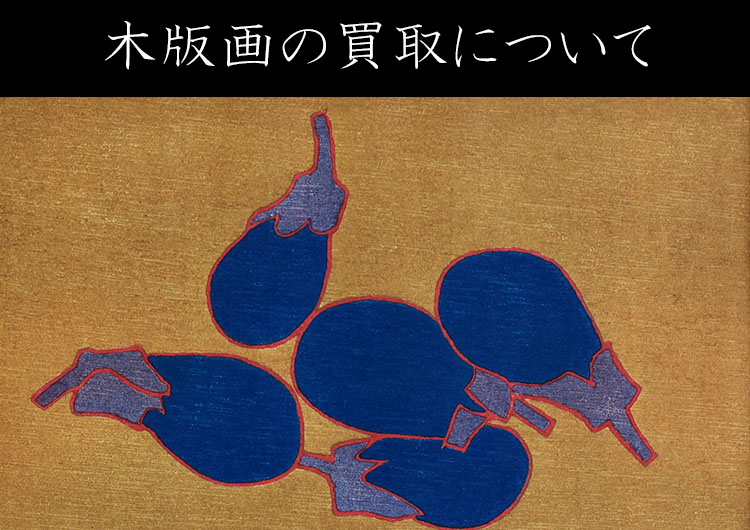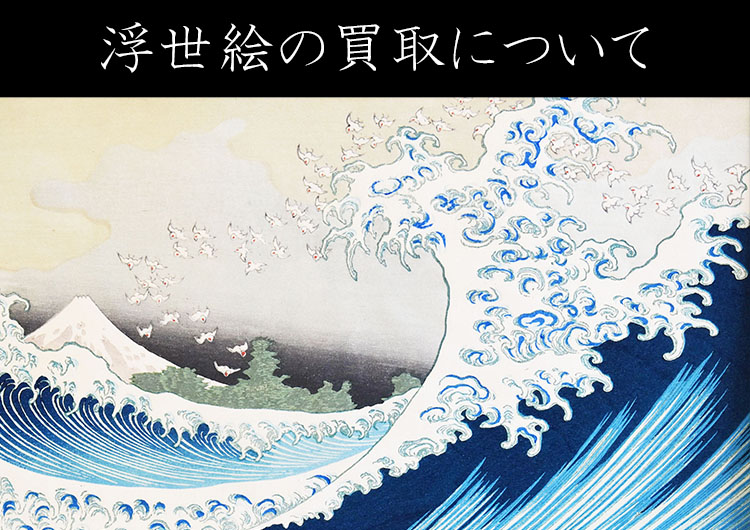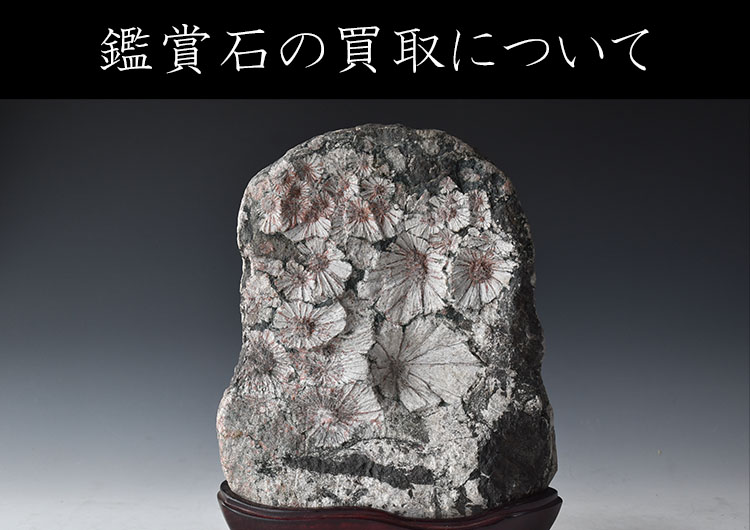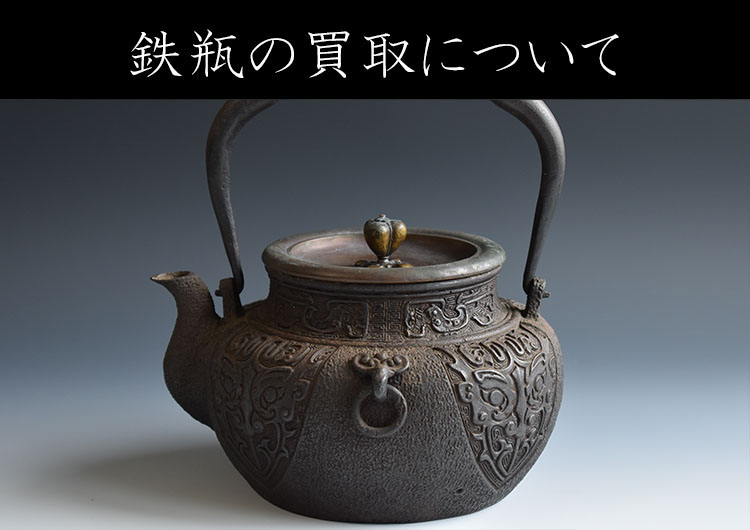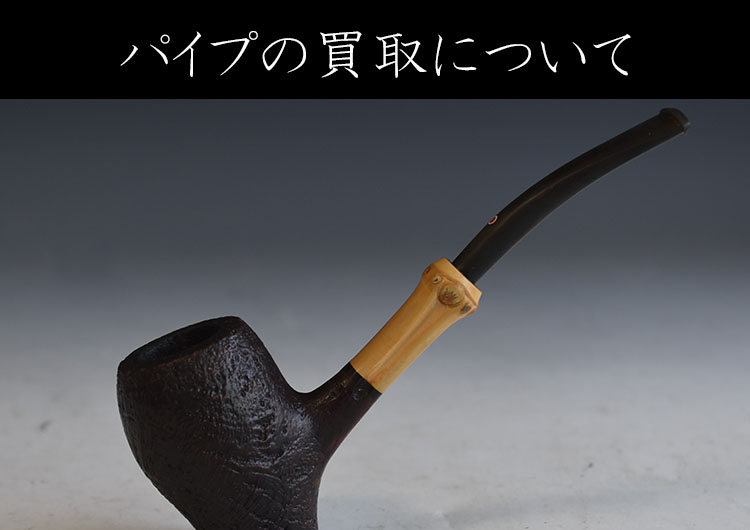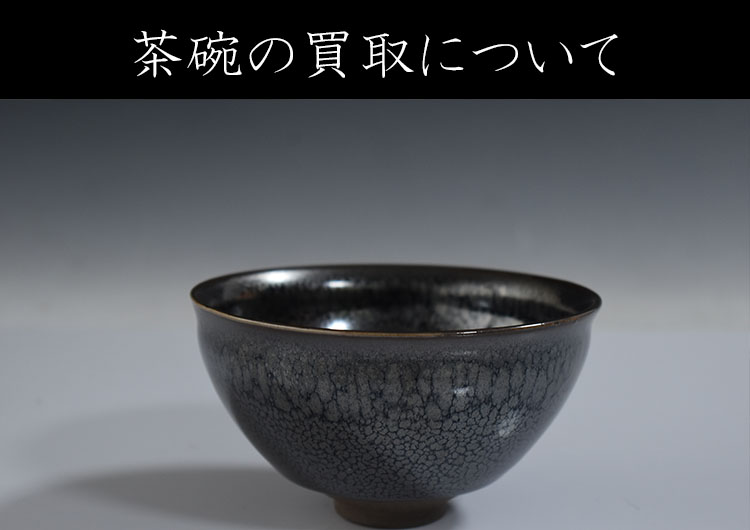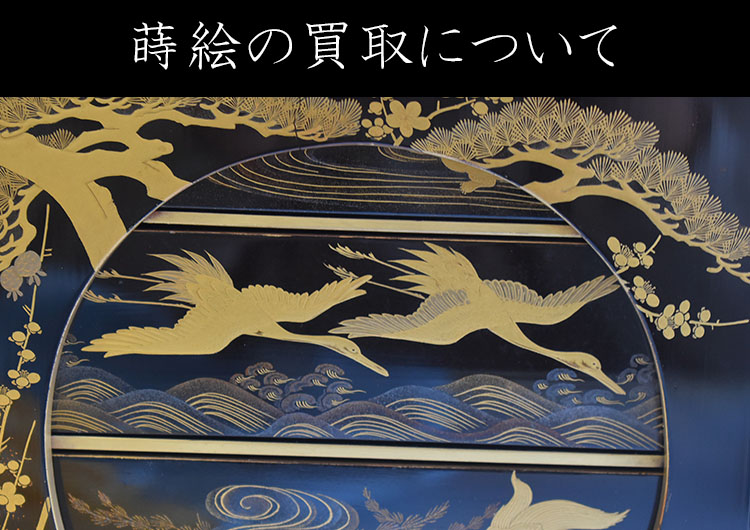白隠慧鶴の買取は三冬花にお任せください。 白隠作品の買取は、三冬花にお任せください。市場の動向に基づいて、白隠の作品の価値を反映した公正な価格をお客様に提案いたします。
白隠慧鶴の略歴 (Hakuin ekaku)
1686年 駿河の原宿で生まれる。 1700年 地元の松蔭寺で出家し、沼津の大聖寺で息道に師事。 1703年 清水の禅叢寺に入るが、後に禅を捨て詩文に没頭。雲棲祩宏の『禅関策進』に触れ修行を再開、諸国を巡る。 1708年 越後の英巌寺で「趙州無字」の公案により開悟。その後、信州の飯山で大悟、嗣法となる。 1710年 京都の北白川で白幽子から「軟酥の法」を学び、禅病が完治。 1716年 遊歴の後、松蔭寺に帰郷。 1763年 三島の龍澤寺を開山。 1769年 松蔭寺で没。
臨済宗中興の祖と称される江戸中期の禅僧。諡は神機独妙禅師、正宗国師。「駿河には過ぎたるものが二つあり、富士のお山に原の白隠」とまで謳われた。現在も、臨済宗十四派は全て白隠を中興としているため、彼の著した「坐禅和讃」を坐禅の折に読誦する。現在、墓は松蔭寺にあって、県指定史跡となり、彼の描いた禅画も多数保存されている。
白隠慧鶴の禅画と墨蹟
白隠は広く民衆に禅の教えを伝えるために努め、多くの絵を描きました。その数は1万点以上とも言われています。最も早い作品は享保4年(1719年)の「達磨図」であり、大作の「達磨図」は寛延4年(1751年)に制作されました。代表作の一つである「大燈国師像」には、下書きや描き直しの跡が残っており、その拙い技法が後の曾我蕭白などに影響を与えたと考えられています。石川九楊は、白隠の墨蹟について「書法の失調」を捉え、「書でなくなることによって書である」と評しています。細川護立と山本発次郎は、白隠の書画の代表的なコレクターであり、それぞれのコレクションは永青文庫と大阪中之島美術館に収められています。
白隠の弟子たち
葦津慧隆 円桂祖純 快嚴智徹 峨山慈棹 央龍伊松 格宗浄超 環渓祖底 貫宗会通 関捩慈訓 寬瑞祖精 玄室宗実 悟庵襌聡 劫運祖永 江西慧顒 業海宗牧 指津宗琅 斯経慧梁 鐘山霊祐 神州義敦 遂翁元廬 石鼎道剛 禅圭周因 滄海宜運 太庾放石 曹渓智脫 草山祖芳 層嶺方邃 太霊紹鑑 大休慧昉 大舟楚欣 大虫慧岑 大同曇慧 長沙恵法 鳥道慧忠 提州禅恕 天崖玄魯 天猊慧謙 東嶺円慈 独天默笑 月丘無隠 弁的首座 澧川道温 牧翁惠水 雄山慧牧 良哉元明 霊源慧桃 楞山慧脫
白隠の出生から雲水としての修行時代
貞享二年(1685年) 東海道十三番目の原宿の地に生まれた白隠(幼名岩次郎) は、元禄十二年(1699年) 十五歳の時に得度して、慧鶴(えかく)と名付けられ る。松蔭寺の見習い僧から修行をはじめ、元禄十六年、十九歳になった慧鶴は廻国行脚へと旅立った。雲水として十四年の歳月を修行に費やすことになるが、各地を遍歴することで、多くの貧しい人々の暮らしの現状を目の当りにした経験は、後年の救済運動に繋がっていった。
故郷原宿にもどり、荒廃していた松蔭寺を復興する
享保二年(1717年)三十三歳で松蔭寺に入寺した慧鶴は、「白隠」という道号を名乗り、松蔭寺の住職に就任する。白隠は、禅の学究に勤しむかたわら、在家支援者の理解と援助のもと、寺の借金を返済しつつ、松蔭寺の復興に精力的に取り組んでいく。その過程で、末寺としての悲哀と苦衷を身に沁みて経験したことは、本末制度に安住する宗門への厳しい批判へと繋がっていった。
社会全体の変革を唱えるようになった後半生への転換
元文二年(1737年)、白隠五十三歳の時に、松蔭寺の経営はようやく軌道にのる。すでにその学識におい名声を博していた白隠は、その年以降、招請に応じては全国各地に赴いて、提唱・講読をおこない、上は公家・大名から下は庶民まで分け隔てなく交流し、社会を深く洞察しては、鋭い疑問、批判を人びとに投げかけた。数万点ともいわれる白隠独得の禅画は、そうした交流のうちに描かれたものである。
宝暦・明和期の白隠
宝暦四年(1754年)、白隠七十歳の時に書かれた『辺鄙以知吾」は、その激烈な政治批判のために禁書となった。また明和年間に駿河小島藩で起こった惣百姓一揆に干与していた可能性もある。幕政・藩政への批判を展開したのは白隠一人ではない。 宝暦八年(1758年)には、京都で竹内式部をはじめとする尊皇論者が弾圧され、明和四年(1767年)には、倒幕思想の先駆けとなる放伐論を唱えた山県大弐が門人らと共に捕縛されるという時代であった。
白隠の門弟、支援者たち
原宿の松蔭寺に参集した門弟たちは、松蔭寺の山号「鵠林」から鵠林一門と呼ばれた。門弟たちの多くは、宗派の有力な寺院、名刹の住職に就任して、白隠の宗門改革を浸透させていった。彼らのほかにも、大名や公家、各地の豪商、豪農などが有力な在家居士となって、白隠の活動をひろく支えていた。鵠林一門に在家居士群を加えれば、まさに鵠林教団とも称すべき一大勢力であった。
白隠の晩年
優秀な数多くの門弟を育て上げ、宗門全体に影響を及ぼすほどにまで拡大した鵠林教団を率いる白隠の権勢は、いまや押しも押されもせぬものであった。そんな白隠が頭を悩ませたこと、それは自身の後継問題であった。五百年に一人と言われた名僧も、晩年はさまざまな俗事に悩まされることになった。後継問題を切り抜けた後、明和五年(1768年)、白隠は八十四歳でその生涯を閉じたのであった。
白隠 買取実績
該当の投稿はありません。
次世代に橋渡しする価値
骨董品や美術品の査定・買取を依頼するのは、人生の中でも大きな決断の一つです。長い年月を共に過ごし、大切にしてきた品。常にご家族の傍らにあり、我が家の歴史そのものと思える品。蔵の中に眠る、先祖代々伝わる品。こうした品を託す際、価値を感じているからこそ「この魅力を理解してくれるだろうか…」「適正な価格で買い取ってもらえる?」と考えるのは当然ですし、それを依頼する業者を選ぶのは容易ではないでしょう。
骨董品や美術品にご興味のない方にとっては、「引き取ってくれればいい」という存在かもしれませんが、実在する品である以上そこには必ず価値があり、信頼できる業者を選ぶのは重要です。三冬花はお客様の大切な品を査定し、買い取りするのにあたり、本当の価値を見きわめ、誠意をもって伝え、適正な価格をお示しすることをお約束します。そのために必要なのが知識と経験です。作品や作家、歴史的背景に関する知識、買い取りから販売までの豊富な経験があってこそ、本当の価値を見きわめることができます。修行や鑑定歴も大事ですが、常に勉強が必要なのは言うまでもありません。私自身、おかげさまで多くの経験を積んできましたが、それでもご依頼にお応えするたびに発見があり、新たな知識を得る日々です。
骨董品、美術品の世界はそれだけ深く、難しいものだと感じています。インターネットの普及で過去の落札価格や買取相場が検索できるようになり、個人売買や多店舗展開の買取店も増えました。身近になったとはいえ依然として特殊な業界でもあり、実態とかけ離れた値付け、経験の浅い鑑定士の査定が珍しくないのも事実です。フランチャイズで大規模に展開すれば、人件費や広告宣伝費、店舗運営費は大きなコストとなり、ひいては買取価格にも反映されます。「いかに安く買い取るか」という発想になるのも避けられません。
骨董品や美術品の買い取りは、極端な言い方をするとお客様の資産を削ることです。私たち業者はそれを自覚し、誠意をもって仕事をする必要があります。三冬花の使命は、その品の本当の価値をみきわめ、その価値を望む方の手元まで適切につなげること。お客様の大切な品を次の世代へつなぐ、そのお手伝いをしています。遺るべき品を後世に遺す。お客様と三冬花の出会いが、そのきっかけになればと願っています。
店舗名 美術三冬花 所在地 〒500-8347 買取・鑑定・査定のお問い合わせ TEL 0120-772-316 古物商許可番号 岐阜県公安委員会第531021300621号 電話受付時間 9:30~17:00 定休日 不定休(店舗にお越しの際は商品の仕入れ、買取業務がありますので、まずはお電話ください)
三冬花で買取できる美術品や骨董品
絵画
掛け軸
古美術品
【骨董品】査定買取の出張エリア
愛知県
名古屋市 /一宮市 /豊田市 /西尾市 /春日井市 /小牧市/稲沢市/津島市/常滑市/豊橋市 /豊川市 /清須市/岡崎市 /安城市 /江南市/岩倉市/豊明市/日進市/北名古屋市/長久手市/東郷町/大口町/扶桑町/弥富市/あま市/大治町/飛鳥村/半田市/大府市/知多市/阿久比町/南知多市/美浜町/武豊町/碧南市/刈谷市 /知立市/高浜市/幸田町/新城市/田原市/設楽町/犬山市/尾張旭市/豊山町/愛西市/蟹江町/東海市/東浦市/みよし市/蒲郡市/東栄町/瀬戸市
岐阜県
岐阜市/羽島市/各務原市 /山県市/瑞穂市/本巣市/岐南町/笠松町/北方町/大垣市 /海津市/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/関市/美濃市/美濃加茂市/可児市/郡上市/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/御嵩町/多治見市/中津川市/瑞浪市/恵那市/土岐市/高山市/飛騨市/下呂市
三重県
桑名市 //四日市市/津市 /いなべ市/木曽岬町/菰野町/朝日町/鈴鹿市/亀山市/多気町/明和町/大台町/鳥羽市/志摩市/玉城町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/尾鷲市/紀北市/熊野市/東員町/川越町/松坂市/伊勢市/度会町/名張市/御浜市/紀宝町
滋賀県
彦根市/甲良町/多賀町/豊郷町/愛荘町/東近江市/日野町/甲賀市/竜王町/大津市/草津市/栗東市/湖南市/守山市/野洲市/近江八幡市/高島市/長浜市/米原市
静岡市内全域(駿河区、葵区、清水区、東区、中区、南区、北区、西区、天竜区、浜北区)/熱海市/沼津市/富士宮市/伊東市/三島市/富士市/島田市/焼津市/掛川市/磐田市/御殿場市/藤枝市/袋井市/裾野市/湖西市/下田市/御前崎市/牧之原市/伊豆市/伊豆の国市/菊川市