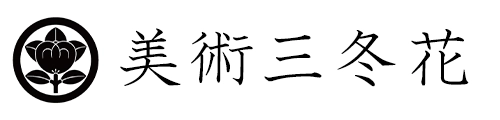人形について
美術三冬花では人形の取り扱いをしております。
【市松人形】
江戸時代の泥人形で、腹の中に笛が仕込んである。京都の市松人形が上手のもので、着せ替えができる衣装も立派である。もと市松という孝子の姿をかたどったものとも、歌舞伎俳優佐野川市松の姿を模したものともいう。また、市松とは江戸時代に多かった童名の一つであったから、市松人形とは単に子供人形の意味であるとする説もある。なお、市松模様の市松とは関係がない。
【一文人形】
江戸の今戸人形の一種で、庶民のための安価な人形として作られた三センチ前後のミニチュア泥人形。型抜きで作り彩色を施しているが、低温で焼いたため脆く、そのためか大量に作られたと思われるが、現存するものは少ない。当時のビタ銭一文で売られたことからこの名がある。
【今戸人形 いまどにんぎょう】
江戸時代初期から第二次世界大戦前まで、江戸・東京のほうろく・火鉢・火消壺など土器の需要を一手に引き受けていた今戸の窯場で、江戸時代中頃より作られ始めた泥人形。
【芋雛 いもびな】
顔が長く、皮をむいたサトイモに似た雛人形。古雛として珍重される。
【宇治人形 うじにんぎょう】
江戸時代から宇治で作られた人形。茶の木を材料として、刀法、彩色とも奈良人形に似ているが、主に茶摘み女の姿に作る。茶の木人形ともいう。
【亀戸人形 かめどにんぎょう】
江戸時代から昭和初期にかけて東京の亀戸天満宮の境内で行われた縁日で売られていた張子人形。いかにも素人の余技によるもののような雑な作りであるが、三河万歳師や通帳で買ってきた酒瓶を持つ男など、人形の姿や顔の表情の面白さに特色がある。
【賀茂人形 かもにんぎょう】
江戸時代後期に京都で作られた木目込み人形。柳や黄楊の木を用いて彫刻し、木目込みに金欄や縮緬の衣装をつけた。ほとんどが五センチ以下の小さな人形である。
【寛永雛 かんえいびな】
江戸時代寛永年間(1624~1644)の名称をもつ十センチ前後の小形の雛人形。頭には髪を植えず、冠と共作りの黒漆となっている。袴の中には綿を入れる。
【芥子雛 けしびな】
江戸時代中期に流行した十センチ以下のごく小型の雛人形。享保六年(1721)幕府 の禁止令によって大型の雛人形の製作が制限された反動で製作されたもので、一寸(約三センチ)以下の雛人形もあった。しかし、次第に精巧で贅沢な作りになり高価になっていったので、これもまた享和三年(1803)幕府によって禁止令が出された。芥子粒のように小さいという意味でこの名がある。
【元禄雛 げんろくびな】
江戸時代元禄年間(1688~1708)の名称をもつ雛人形。男雛は頭に髪を植えず、冠と共作りで黒漆塗りである。女雛は袖口や裾を重ねた十二単風の五衣の姿で表し、袴には綿を入れてふくらませており、この後の享保雛の祖型として位置づけられる。